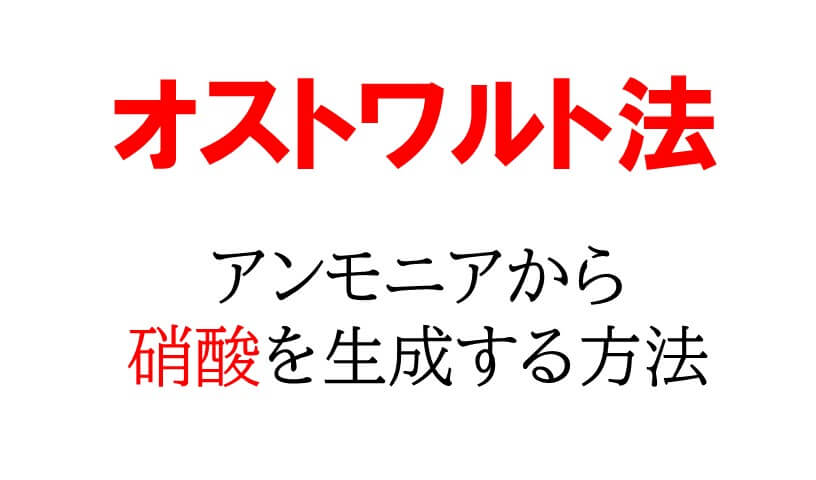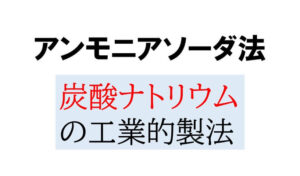オストワルト法とは?
オストワルト法とは、アンモニア(NH₃)と酸素(O₂)を出発物質として、硝酸(HNO₃)を工業的に合成する方法です。現在でも、世界中の工場で実際に利用されている代表的な窒素化合物の製法です。
硝酸は、肥料や火薬、染料、医薬品など、幅広い分野で使われる重要な化合物です。そのため、大量生産できる仕組みが確立されており、その中心となっているのがこのオストワルト法です。
具体的には以下の3段階で進みます。
- アンモニアと酸素から 一酸化窒素(NO) と水をつくる
- 一酸化窒素をさらに酸化して 二酸化窒素(NO₂) に変える
- 二酸化窒素を水に溶かして 硝酸(HNO₃) を得る
この3つの反応をまとめると、次のように表せます。
$$
NH₃ + 2O₂ → HNO₃ + H₂O
$$
ただし、この式は実際の細かい反応を省略した「まとめの式」であり、実際には触媒や反応条件を工夫して、順を追って進行させる必要があります。
オストワルト法の反応式まとめ
オストワルト法では、アンモニアから硝酸ができるまでに 3つの反応段階 があります。それぞれの反応式を確認していきましょう。
アンモニアと酸素から一酸化窒素を生成(触媒:白金)
まず、アンモニアを酸化して 一酸化窒素(NO) をつくります。この反応は白金(Pt)を触媒として高温で行われます。
$$
4NH₃ + 5O₂ → 4NO + 6H₂O
$$
ここでできる NO が次の反応の出発物質となります。
覚え方のポイント
- 反応物は「NH₃」と「O₂」、生成物は「NO」と「H₂O」。
- Nの数をそろえる:NH₃はNが1個 → NOもNが1個 → 係数は同じ「4」でそろえる。
- Hの数をそろえる:4NH₃にHが12個 → H₂Oで12個に合わせる → H₂Oに係数6。
- 最後に Oの数を調整:右辺で4(NO)+6(H₂O)=10個 → 左辺のO₂を5にする。
👉 「Nをそろえる → Hをそろえる → Oを最後にそろえる」流れが基本。
一酸化窒素と酸素から二酸化窒素を生成
次に、一酸化窒素を酸素で酸化して 二酸化窒素(NO₂) を得ます。
$$
2NO + O₂ → 2NO₂
$$
この反応は自然に進行し、赤褐色の気体であるNO₂が生成します。
二酸化窒素を温水に溶かして硝酸を生成
最後に、二酸化窒素を水に溶かすと 硝酸(HNO₃) が得られます。
$$
3NO₂ + H₂O → 2HNO₃ + NO
$$
この反応では一部NOが戻ってきますが、再び酸化されて循環的に利用されるため、効率よく硝酸をつくることができます。
覚え方のポイント
- 「NO₂が水に溶けるとHNO₃ができるが、一部NOに戻る」ことを理解しておく。
- Nの数:NO₂が3個 → 生成物はHNO₃(2個)+NO(1個)でNは合計3個。
- Hの数:H₂Oが2個 → HNO₃のHが2個でつり合う。
- Oの数:左辺は3×2(NO₂)+1(H₂O)=7個。右辺はHNO₃(2×3)+NO(1)=7個。バランス良し。
👉 このように、オストワルト法は「アンモニア → NO → NO₂ → HNO₃」という流れで進行します
まとめ方のポイント
1. 3つの式を並べる
① アンモニアの酸化
$$
4NH₃ + 5O₂ → 4NO + 6H₂O
$$
② 一酸化窒素の酸化
$$
2NO + O₂ → 2NO₂
$$
③ 二酸化窒素を温水と反応させる
$$
3NO₂ + H₂O → 2HNO₃ + NO
$$
2. 中間生成物を打ち消す
- NO(①で生成 → ②で消費 → ③で再登場)
- NO₂(②で生成 → ③で消費)
このように、中間物質は最終的に残らないので 式の両辺から打ち消してよい。
- ②③式のNO₂の係数を6にそろえる。そのため3×②、2×③とする。
- ①+3×②+2×③を計算する
以上の作業を行うだけで簡単に中間物質NO、NO₂を式から消すことができます。
$$
4NH₃ + 8O₂ → 4HNO₃ + 4H₂O
$$
3. 係数を簡略化する
3つの式をすべて足すとやや大きな数になりますが、最後に 4で割って最小整数比 にそろえると、
$$
NH₃ + 2O₂ → HNO₃ + H₂O
$$
となります。
覚え方のコツ
- 「中間生成物は消してよい」 → 反応の途中で姿を消すもの(NO, NO₂)はまとめ式に残らない。
- 最後に整数比で整理 → 大きな数が出ても約分してシンプルに。
- 「アンモニアと酸素 → 硝酸と水」という形を頭に入れておくと入試問題で迷わない。