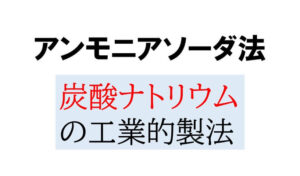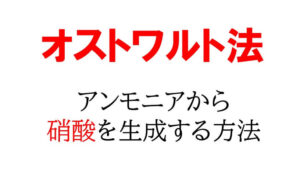核酸とは?|細胞内で重要な“情報のもと”
- 細胞内にある高分子化合物
- DNAとRNAの2種類
- ヌクレオチドが縮合結合した「ポリヌクレオチド」
生物の体をつくる「設計図」を担っている物質が核酸(かくさん)です。核酸は、遺伝情報を記録し、それをもとにタンパク質を合成するという、生き物にとって根本的な役割を担っています。高校化学では、「DNA」と「RNA」の2つが登場します。
核酸は「DNA」と「RNA」の2種類
核酸には大きく分けて、
- DNA(デオキシリボ核酸)
- RNA(リボ核酸)
の2種類があります。
| 核酸の種類 | 主な役割 | 存在場所 |
|---|---|---|
| DNA | 遺伝情報の保存と伝達 | 主に細胞の核内 |
| RNA | タンパク質合成の補助 | 核内・細胞質(リボソームなど) |
DNAは「親から子へ情報を伝える役割」、RNAは「DNAの情報をもとにタンパク質をつくる仲介役」とイメージすると覚えやすくなります。
基本構造はヌクレオチドの連なり(ポリヌクレオチド)
DNAもRNAも、「ヌクレオチド」と呼ばれる小さな単位が鎖のようにつながった高分子化合物(ポリヌクレオチド)です。ヌクレオチドは以下の3つのパーツから構成されています。
- 糖(五炭糖)
- リン酸
- 塩基
糖の種類によって、DNAでは「デオキシリボース」、RNAでは「リボース」が使われます。また、塩基の種類や鎖の構造も異なるため、このあと詳しく比較していきます。
💡【チェックポイント】
「核酸=ヌクレオチドがたくさんつながったもの」と整理しておこう。入試ではこの構造の違い(糖や塩基の違い)を問われることが多い!
DNA(デオキシリボ核酸)の特徴
DNAは、すべての生物がもつ遺伝情報の本体です。細胞分裂やタンパク質合成の設計図として機能し、「親から子へ情報を伝える」重要な役割を担っています。
| どこにある? | 細胞の核 |
| 何構造? | 二重らせん構造 |
| 役割は? | 遺伝情報を伝える |
どこにある? → 核の中
DNAは、主に真核細胞の「核」に存在します。ヒトを含む多くの動物・植物の細胞では、核膜で囲まれた核の中に、染色体の形で存在しています。
構造は? → 二重らせん構造
DNAは、二本のポリヌクレオチド鎖がらせん状に巻きついた「二重らせん構造」をしています。
- 2本の鎖は塩基の相補性によって結合
- らせんの中に塩基、外側に糖とリン酸が並ぶ
🧠「ハシゴをねじったような形」とイメージすると覚えやすい!
役割は? → 遺伝情報の保存と伝達
DNAは、生物がもつあらゆる形質(性質や特徴)を決定する情報を保持しています。この情報は塩基配列(A・T・G・Cの並び)として記録されており、以下のように利用されます。
- 細胞分裂時に複製され、次世代へ伝達される
- 必要なときにRNAを通じてタンパク質合成に活用される
DNAのヌクレオチド構造(糖・リン酸・塩基)
DNAのヌクレオチドは以下の3つで構成されます:
- 糖:デオキシリボース(五炭糖)
- リン酸
- 塩基:A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)
この「塩基」が情報のカギであり、4種類の塩基の並び順が遺伝情報を表します。
DNAの塩基はA・T・G・Cの4種類
DNAの塩基は以下の4種類:
| 塩基名 | 略号 |
|---|---|
| アデニン | A |
| チミン | T |
| グアニン | G |
| シトシン | C |
これらは相補的に結合し、以下のペアで2本鎖を形成します:
- A ⇔ T(アデニンとチミン)
- G ⇔ C(グアニンとシトシン)
✅「AはTと、GはCと対になる」ルールは必ず覚えておこう!
RNA(リボ核酸)の特徴
| どこにある? | 細胞の核・細胞質 |
| 何構造? | 1本鎖状構造 |
| 役割は? | タンパク質合成に関与する |
RNAは、DNAの情報をもとにしてタンパク質を合成するサポート役を担う核酸です。RNAはDNAと異なる構造・働きをもち、「情報の使い方」を担当する分子といえます。
どこにある? → 核と細胞質
RNAは、細胞の核内と細胞質の両方に存在します。また、RNAには複数の種類があり、それぞれ役割が異なります。
| 種類 | 働き |
|---|---|
| mRNA(メッセンジャーRNA) | DNAの情報を写しとって運ぶ |
| tRNA(トランスファーRNA) | アミノ酸を運んでくる |
| rRNA(リボソームRNA) | タンパク質合成の場を構成 |
構造は? → 一本鎖構造
RNAは、1本のポリヌクレオチド鎖からなる「一本鎖構造」です。DNAのように二重らせんにはなりません。
役割は? → タンパク質合成のサポート
RNAの主な役割は、DNAに保存されている情報を読み取り、それをもとにタンパク質を合成することです。
RNAのヌクレオチド構造(糖・リン酸・塩基)
RNAのヌクレオチドは以下の3つの要素で構成されます:
- 糖:リボース(DNAと違い、酸素原子が1つ多い)
- リン酸
- 塩基:A(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、U(ウラシル)
糖の違いにより、RNAはDNAよりも化学的に不安定ですが、その分「一時的な情報の伝達」に適しています。
RNAの塩基はA・U・G・Cの4種類(※Tの代わりにU)
RNAの塩基は以下の4種類です:
| 塩基名 | 略号 | 備考 |
|---|---|---|
| アデニン | A | DNAと共通 |
| ウラシル | U | RNA特有(Tの代わり) |
| グアニン | G | DNAと共通 |
| シトシン | C | DNAと共通 |
✅RNAではチミン(T)の代わりにウラシル(U)を使うのが最大の特徴です。入試でよく「DNAとRNAの塩基の違い」が問われるので、しっかり覚えておきましょう。
DNAとRNAの違いまとめ
DNAとRNAはどちらも核酸ですが、構造・成分・役割の面で明確な違いがあります。受験では「違いを1つ選べ」「共通点を選べ」などの形式でよく問われるため、以下の表でしっかり整理しておきましょう。
| 項目 | DNA(デオキシリボ核酸) | RNA(リボ核酸) |
|---|---|---|
| 糖の種類 | デオキシリボース | リボース |
| 塩基の種類 | A・T・G・C | A・U・G・C(Tの代わりにU) |
| 鎖の構造 | 二重らせん(二本鎖) | 一本鎖 |
| 存在場所 | 核(真核細胞) | 核・細胞質(リボソームなど) |
| 主な役割 | 遺伝情報の保存・伝達 | タンパク質合成のサポート |
覚え方のコツと確認問題
違いを覚えるときは、図や語呂合わせ、具体例を使ってイメージとセットで記憶するのが効果的です。
A・G・Cは共通|Aの後が違う
DNA、RNAの塩基配列は以下の通りです。
- DNAの塩基:A・T・G・C
- RNAの塩基:A・U・G・C
まずは「A・G・Cは共通」と覚えましょう。そして、「DNA→T」「RNA→U」というように覚えます。
確認問題(○×形式)
以下の問題で知識の定着を確認しましょう。
Q1. RNAの塩基にはチミン(T)が含まれる。
→ ×(ウラシル U)
Q2. DNAは1本鎖、RNAは2本鎖である。
→ ×(逆)
Q3. DNAとRNAの両方に含まれる塩基は、A・G・Cである。
→ ○
Q4. DNAとRNAでは、糖の種類が異なる。
→ ○(DNA=デオキシリボース、RNA=リボース)
Q5. RNAはタンパク質合成に関与しない。
→ ×(むしろ中心的役割!)