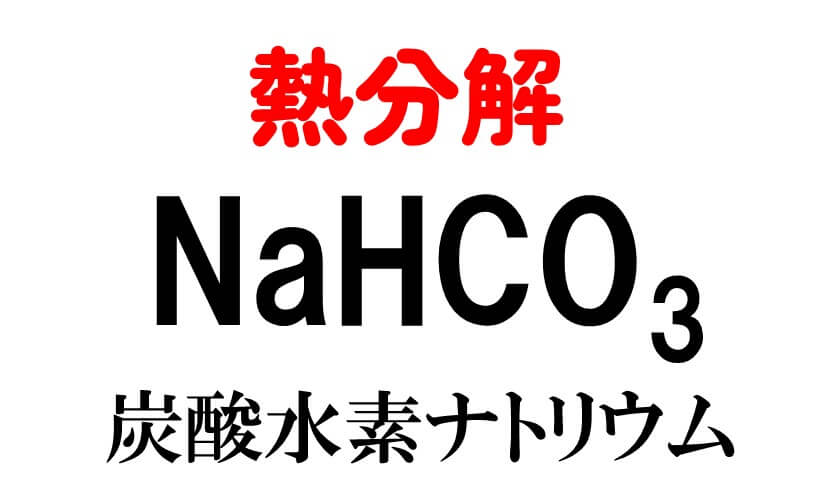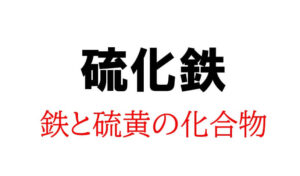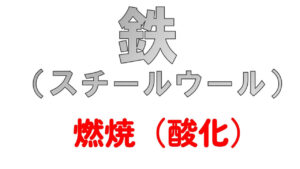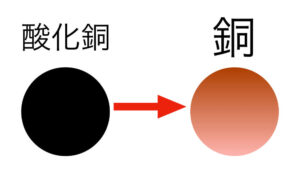炭酸水素ナトリウムとは?
炭酸水素ナトリウムは、白い粉の物質で、化学式は NaHCO₃ と書きます。別名を「重曹(じゅうそう)」 といい、理科の授業だけでなく、私たちの生活の中でもよく使われています。
たとえば、次のような身近な使い道があります。
- お菓子作り:ケーキやクッキーをふくらませる「ふくらし粉」として使われます。
- 掃除:油汚れを落としたり、においを取ったりするのに使われます。
- 胃薬:胃酸を中和して、胸やけを抑える薬の成分として使われます。
このように、炭酸水素ナトリウムは身近でとても役立つ物質です。
次に、この炭酸水素ナトリウムを加熱するとどうなるのか、熱分解についてくわしく見ていきましょう!
炭酸水素ナトリウムの熱分解
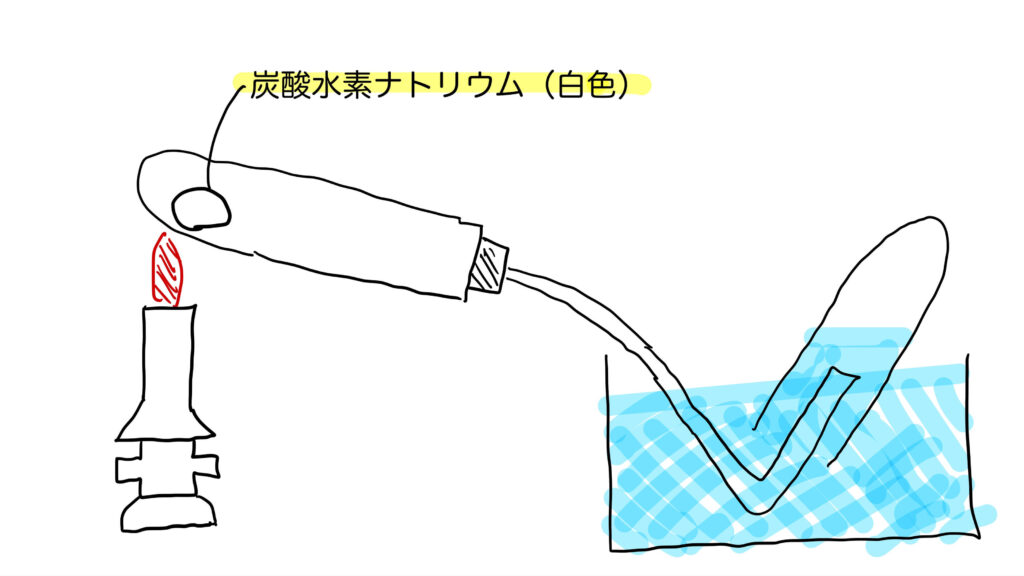
炭酸水素ナトリウムを熱すると、別の物質と気体に分かれる反応を「熱分解(ねつぶんかい)」といいます。
化学反応式
炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式は、次のように表します。
2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O
この式の意味は次のとおりです。
- 炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)を2つ加熱すると、
- 炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)と
- 二酸化炭素(CO₂)、
- 水(H₂O)
ができます。
覚え方のポイント
- 炭酸水素ナトリウムが熱分解するると、固体、液体、気体の3つの物質ができる。
- 固体:炭酸ナトリウム
- 液体:水
- 気体:二酸化炭素
発生する物質の性質と確認方法
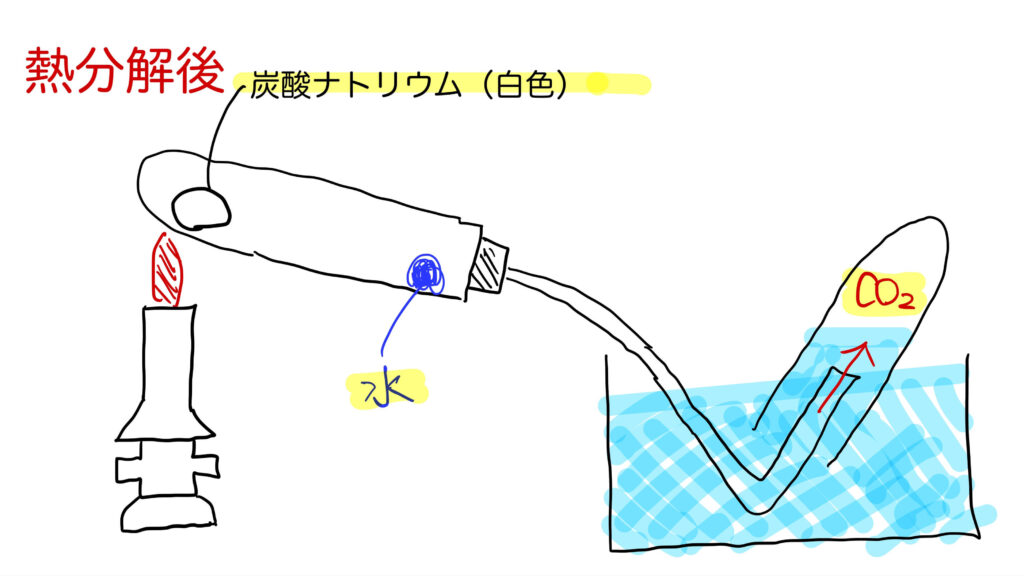
炭酸水素ナトリウムを熱分解すると、炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)と二酸化炭素(CO₂) と 水(H₂O) が発生します。これらの物質には、それぞれ調べる方法があります。
二酸化炭素の確認方法
二酸化炭素が発生したかどうかを確かめるには、石灰水(せっかいすい) を使います。
二酸化炭素を石灰水に通すと、次のようになります。
石灰水が白くにごる(白く濁る)
この性質を利用して、二酸化炭素の発生を調べます。理科のテストにもよく出るポイントです!
水の確認方法
水(H₂O)も熱分解で出てきます。水が発生したかどうかは、塩化コバルト紙(えんかコバルトし) を使うと調べられます。
塩化コバルト紙は、乾いていると青色ですが、水蒸気がつくと赤色に変わります。
この色の変化を利用して、水が出ているかを確認します。
炭酸ナトリウムの確認
炭酸水素ナトリウムを熱分解した後、試験管の中には白い粉が残ります。これが炭酸ナトリウム(Na₂CO₃) です。
炭酸ナトリウムは、見た目は白い粉で、炭酸水素ナトリウムと色は同じです。でも、性質にはちがいがあります。
水によく溶けてアルカリ性を示す
炭酸ナトリウムは水によく溶けて、その水溶液はアルカリ性になります。アルカリ性の水溶液は、フェノールフタレイン液を赤色にしたりする性質です。
炭酸ナトリウムは、炭酸水素ナトリウムよりも強いアルカリ性を持っていて、フェノールフタレイン液をよりはっきりと赤くします。
炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの比較
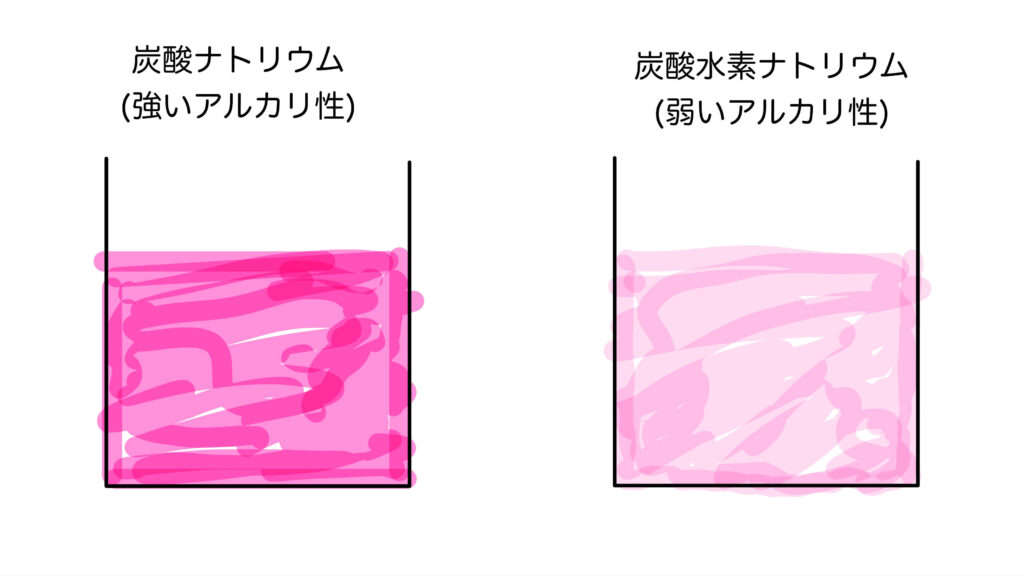
一方、炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)は、水に少し溶けます。その水溶液は弱いアルカリ性になります。
このとき、フェノールフタレイン液(フェノールフタレインえき) を入れると、うすい赤色になります。
色がうすいのは、アルカリ性がそれほど強くないからです。
比較表をまとめておきます。
| 炭酸水素ナトリウム | 炭酸ナトリウム | |
| 水への溶け方 | 少し溶ける | 解く溶ける |
| フェノールフタレイン液 の変化 | うすい赤色→弱いアルカリ性 | 濃い赤色→強いアルカリ性 |
このように、炭酸水素ナトリウムの熱分解で発生する気体には、それぞれ調べ方があります。以上は、テストで頻繁に問われるので、ぜひ覚えておきましょう!
実験の注意点
炭酸水素ナトリウムの熱分解の実験では、次の2つに注意します。
試験管の口を下向きにする
加熱部に水が流れ込むと、試験管内の圧力で試験管が割れてしまうおそれもあります。安全のためにも試験管の口は下向きにするのです。
火を消す前にガラス管を水槽から取り出す
加熱をやめると、試験管内の圧力が下がるので、水槽の水が試験管内に逆流してくる可能性があります。それをふせぐために、火を消す前にガラス管を水槽から取り出しておきます。