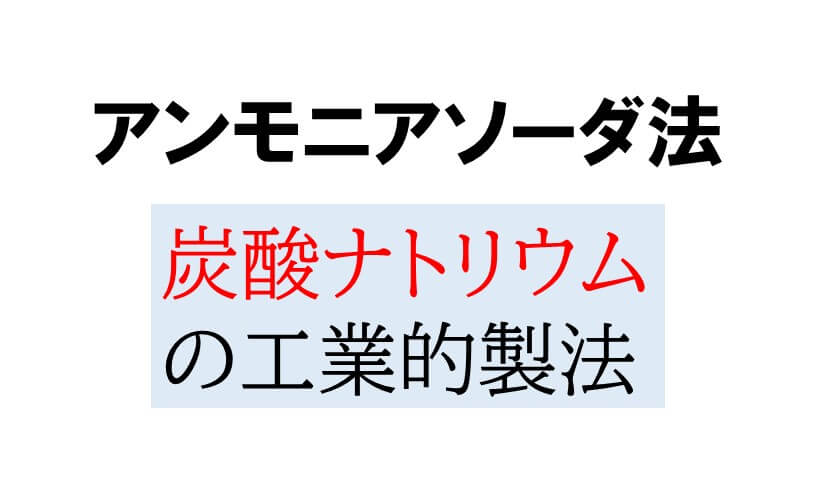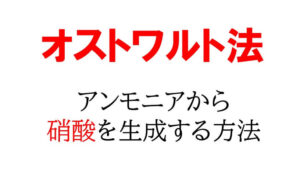アンモニアソーダ法とは?
食塩と石灰石から炭酸ナトリウムをつくる工業的製法
アンモニアソーダ法とは、塩化ナトリウム(NaCl)=食塩と、炭酸カルシウム(CaCO₃)=石灰石を原料にして、炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)=ソーダ灰をつくる工業的製法です。
2NaCl + CaCO₃ → Na₂CO₃ + CaCl₂
炭酸ナトリウムは、ガラス工業・石けん・紙・洗剤など、幅広い分野で利用される重要な物質です。そのため、この製法は19世紀以降、化学工業を大きく発展させる基盤となりました。
原料のうち、食塩は海水から大量に得られ、石灰石も地殻に豊富に存在するため、原料の確保が容易であることも大きな利点です。
なぜ「アンモニアソーダ法」と呼ばれるのか
炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)=ソーダ灰が生成されるので「ソーダ」がつくのは納得です。では、なぜ「アンモニア」がつくのでしょうか?
アンモニアソーダ法の最大の特徴は、アンモニア(NH₃)が反応の媒介として使われる点です。
実際の反応では、食塩水にアンモニアと二酸化炭素を通じることで、炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)が沈殿として得られます。その後、炭酸水素ナトリウムを加熱分解することで炭酸ナトリウムが得られます。
ここで使われたアンモニアは、最後に塩化アンモニウム(NH₄Cl)と水酸化カルシウムの反応によって再生され、再び反応に利用されます。
つまり、アンモニアは反応のサイクルを回す「触媒的な役割」を果たしており、このことから「アンモニアソーダ法」と呼ばれています。
アンモニアソーダ法の反応式|5つの過程
① NaCl・NH₃・H₂O・CO₂ → NaHCO₃ + NH₄Cl
まず、**飽和食塩水(NaCl水溶液)**にアンモニア(NH₃)と二酸化炭素(CO₂)を吹き込むと、**炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)と塩化アンモニウム(NH₄Cl)**が生成します。
このとき、炭酸水素ナトリウムは水に溶けにくく沈殿として析出するので、分離が可能です。
② NaHCO₃ → Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O(熱分解)
得られた炭酸水素ナトリウムを加熱すると、**炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)**に変化します。同時に二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)が発生します。
これが目的物である「ソーダ灰」です。
③ CaCO₃ → CaO + CO₂(熱分解)
別工程では、原料である石灰石(CaCO₃)を強く加熱して、**酸化カルシウム(CaO)**と二酸化炭素(CO₂)を得ます。
ここで発生したCO₂は、①の反応に再利用されます。
④ CaO + H₂O → Ca(OH)₂(水和反応)
次に、生成した酸化カルシウムに水を加えると、**水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)**ができます。
これは消石灰とも呼ばれ、⑤の反応で使用されます。
⑤ 2NH₄Cl + Ca(OH)₂ → 2NH₃ + 2H₂O + CaCl₂
最後に、①で副生成した**塩化アンモニウム(NH₄Cl)と④でつくった水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)**を反応させます。
するとアンモニア(NH₃)が再び生成し、工程①に戻して利用できるのです。これにより、アンモニアは反応のサイクルを回す「触媒的な役割」を果たしています。
👉 この5つの反応を組み合わせて不要な中間生成物を消去すると、最終的に次の単純な式が得られます。
2NaCl + CaCO₃ → Na₂CO₃ + CaCl₂
つまり「食塩(NaCl)と石灰石(CaCO₃)から炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)ができる」というのが、アンモニアソーダ法の本質です。
アンモニアソーダ法の覚え方のポイント
まず全体の式を覚える
アンモニアソーダ法の反応式は、最終的に不要な中間生成物を消すことで次のようにまとまります。
2NaCl + CaCO₃ → Na₂CO₃ + CaCl₂
細かい過程を覚える前に、「食塩と石灰石からソーダ灰ができる」このシンプルな形をまず頭に入れておきましょう。
①~⑤式は3つに大別する
細かく5段階ある反応式を、そのまま丸暗記するのは大変です。ポイントは、流れを3つのグループに整理して理解することです。
①②の手順がメイン|アンモニアから炭酸ナトリウムができるとイメージ
- ① NaCl・NH₃・H₂O・CO₂ → NaHCO₃ + NH₄Cl
- ② NaHCO₃ → Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O
ここがアンモニアソーダ法の中心部分です。
アンモニアと二酸化炭素を使って「炭酸水素ナトリウム」をつくり、それを熱分解して「炭酸ナトリウム」を得る――名前の通り「アンモニア」から「ソーダ」ができる流れをイメージすると覚えやすいです。
③④を1つの流れとして整理
- ③ CaCO₃ → CaO + CO₂
- ④ CaO + H₂O → Ca(OH)₂
こちらは「石灰石から消石灰をつくる流れ」としてひとまとめにして覚えましょう。
ここで得られるCO₂は①で、水酸化カルシウムは⑤で利用されます。
塩化アンモニウムからアンモニアを生成して①で再利用
- ⑤ 2NH₄Cl + Ca(OH)₂ → 2NH₃ + 2H₂O + CaCl₂
最後に、①で生成した塩化アンモニウムと⑤で生成した水酸化カルシウムからアンモニアを再生します。これを再び①に戻すことで、アンモニアが循環的に利用できるわけです。
✅ ポイントは「①②がメイン」「③④は補助工程」「⑤でアンモニアを再生」という3つのまとまりで理解すること。
こう整理すると、入試でも混乱せずに反応式を思い出せます。