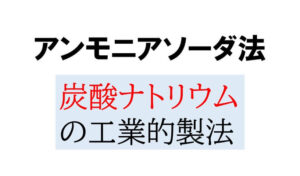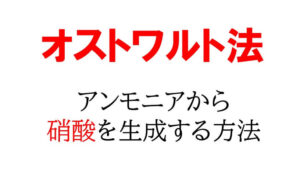高校化学でよく出てくる「金属と酸の反応」。その中でも 銅(Cu)と硝酸(HNO₃)の反応 は入試でも頻出です。特に、希硝酸と反応した場合は、通常の酸では見られない特殊な化学反応式が登場します。さらに、この反応を理解するには、半反応式の考え方や酸化還元反応式の整理が不可欠です。
本記事では、銅と希硝酸の反応を徹底解説し、発生する気体の性質や確認方法まで詳しく紹介します。定期テスト対策から大学入試まで役立つ内容です。
銅と希硝酸の反応とは?
銅はなぜ酸に溶けにくいのか
銅(Cu)は、塩酸や希硫酸のような通常の酸には反応せず、溶けません。これは銅のイオン化傾向が小さく、水素よりも電子を放出しにくい金属だからです。そのため、「H⁺と置換」する反応は起こらないのです。
濃硝酸と希硝酸の違い
ところが、硝酸(HNO₃)は強い酸化力を持つため、銅を溶かすことができます。
- 濃硝酸:銅と反応して二酸化窒素(NO₂)が発生。赤褐色の有毒な気体。
- 希硝酸:銅と反応して一酸化窒素(NO)が発生。その後空気中で酸化されNO₂になる。
ここでは、銅+希硝酸の反応に焦点を当てて見ていきます。
銅と希硝酸の化学反応式
全体の化学反応式
銅と希硝酸が反応すると、以下の化学反応式で表されます。
[
3Cu + 8HNO₃ → 3Cu²⁺ + 2NO + 4H₂O + 6NO₃⁻
]
水溶液中では銅イオン(Cu²⁺)と硝酸イオン(NO₃⁻)が存在するので、実際には硝酸銅(Cu(NO₃)₂)が生成します。整理すると次のようになります。
[
3Cu + 8HNO₃ → 3Cu(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O
]
この式が入試でよく問われる化学反応式です。
半反応式から導く方法
化学反応式は「半反応式」を組み合わせることで確認できます。
- 酸化半反応(銅が酸化される):
[
Cu → Cu^{2+} + 2e⁻
] - 還元半反応(硝酸イオンが還元される):
[
2NO₃⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ → 2NO₂ + 2H₂O
]
希硝酸の場合は発生する気体がNOになるため、還元反応を調整すると:
[
2NO₃⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ → 2NO + 2H₂O
]
- 酸化・還元半反応を足し合わせて酸化還元反応式を完成させる。
酸化還元反応式としての整理
酸化還元反応式をまとめると、銅は電子を失い(酸化)、硝酸イオンは電子を受け取って還元されます。
つまり、銅+希硝酸の反応は 典型的な酸化還元反応式として整理できるのです。
反応で発生する気体の性質
一酸化窒素(NO)が生じる仕組み
希硝酸で銅を溶かすと、一酸化窒素(NO)が発生します。NOは無色・無臭の気体で、発生直後は目立ちません。
空気中で二酸化窒素(NO₂)に変化
発生したNOは空気中の酸素と反応し、二酸化窒素(NO₂)に変化します。NO₂は赤褐色で強い刺激臭を持ち、実験室ではすぐに確認できます。
[
2NO + O₂ → 2NO₂
]
発生する気体の確認方法
- 発生直後は無色 → NO
- 空気に触れると赤褐色 → NO₂
- 実験で見られる「最初は透明、しばらくすると赤褐色に変わる」現象は、この変化によるものです。
入試での出題例と学習のコツ
頻出する金属と酸の反応問題
入試では「金属と酸の反応」がよく問われます。特に「銅は塩酸に溶けないが、硝酸には溶ける」という性質が狙われます。
発生する気体に注目する出題パターン
問題例:
「銅を希硝酸に加えたときに発生する気体は何か?」
→ 正解は 一酸化窒素(NO)。
「発生した気体が空気に触れるとどうなるか?」
→ 二酸化窒素(NO₂)に変化し、赤褐色の刺激臭を持つ。
このように、「発生する気体」を答えさせる問題は頻出です。
まとめ|銅と希硝酸の反応を得点源に
- 銅は塩酸では溶けないが、硝酸には溶ける。
- 化学反応式:
[
3Cu + 8HNO₃ → 3Cu(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O
] - 半反応式・酸化還元反応式の典型例。
- 発生する気体はNOで、空気中でNO₂に変化。
- 入試では「気体の性質」と「濃硝酸との違い」が問われやすい。
高校化学の重要テーマなので、必ず押さえておきましょう。
一問一答(確認問題)
Q1:銅はなぜ塩酸に溶けないのか?
→ イオン化傾向が小さく、水素イオンより電子を失いにくいため。
Q2:銅と希硝酸の化学反応式を書け。
→ (3Cu + 8HNO₃ → 3Cu(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O)
Q3:この反応を酸化還元反応式で整理するとどうなるか?
→ 銅は酸化、硝酸イオンは還元される。
Q4:発生する気体と、その後の変化は?
→ NO(無色)→ 空気中で酸化されNO₂(赤褐色)になる。