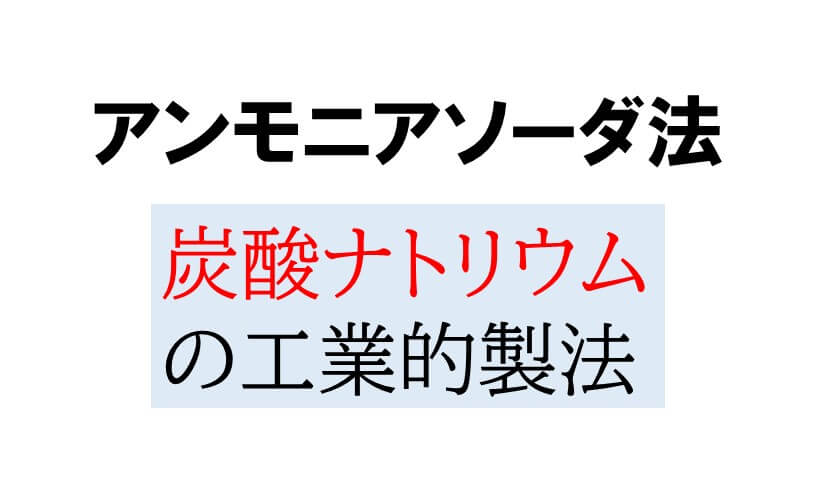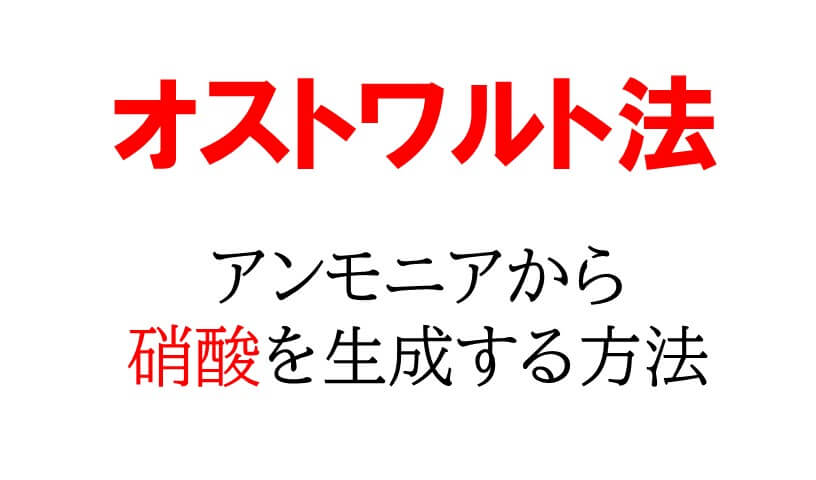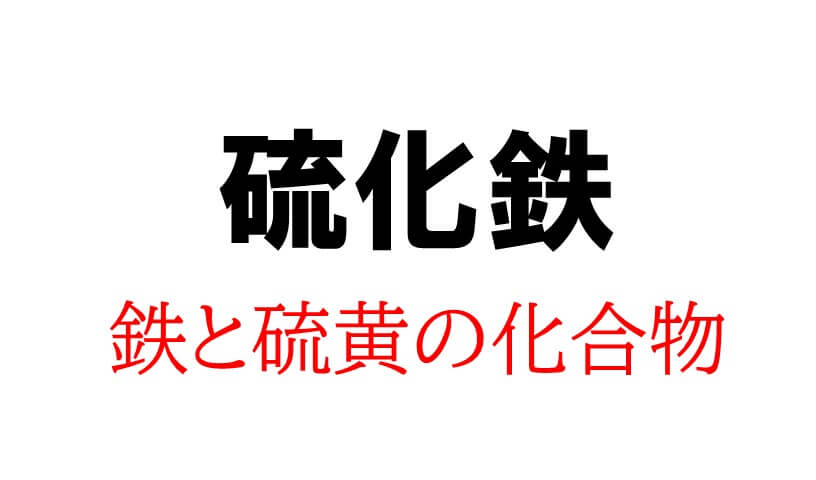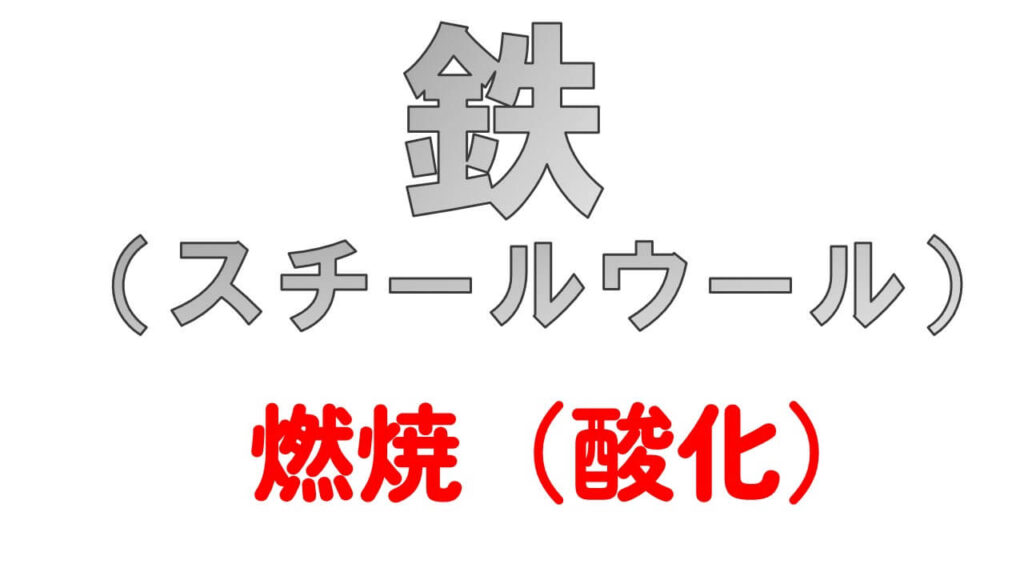-

ばね振り子の単振動の仕組みを解説|復元力・周期の求め方
単振動とは何か?|ばねの運動との関係を理解しよう 単振動とは、「ある1点(振動中心)に戻ろうとする力」が常にはたらき、往復運動をする運動のことです。ばねにつながれた物体が左右に揺れる運動は、まさに単振動の代表例です。 物体が右にずれれば左... -

銅と希硝酸の反応式を徹底解説|化学反応式・半反応式・発生する気体まで
高校化学でよく出てくる「金属と酸の反応」。その中でも 銅(Cu)と硝酸(HNO₃)の反応 は入試でも頻出です。特に、希硝酸と反応した場合は、通常の酸では見られない特殊な化学反応式が登場します。さらに、この反応を理解するには、半反応式の考え方や酸... -

【中学理科】中和反応とは?わかりやすい説明と身近な例
中和反応は中学理科の中でも、酸・アルカリの性質を理解するうえでとても大切な単元です。「酸とアルカリが混ざるとどうなるの?」「どんな身近な例があるの?」と疑問に思う中学生も多いでしょう。この記事では、中和反応の基本から、わかりやすい例、反... -

【中3理科】イオンの化学式一覧
中学3年生の理科で学ぶ「イオン」は、テストや入試で必ず出題される重要単元です。「化学式をまとめて確認したい」「陽イオンと陰イオンの違いを整理したい」という人のために、この記事では 中3で覚えるべきイオンの一覧表 をわかりやすくまとめました。... -

塩化銅水溶液の電気分解|色の変化と陽極・陰極の反応をわかりやすく解説
理科の授業で出てくる塩化銅水溶液の電気分解。「陽極ではどんな気体が発生するのか?」「陰極では何が起こるのか?」さらに、「なぜ溶液の青色がだんだんうすくなるのか?」この記事では、実験装置のしくみから反応式まで、入試によく出るポイントを中学... -

アンモニアソーダ法|反応式の覚え方のコツ
アンモニアソーダ法とは? 食塩と石灰石から炭酸ナトリウムをつくる工業的製法 アンモニアソーダ法とは、塩化ナトリウム(NaCl)=食塩と、炭酸カルシウム(CaCO₃)=石灰石を原料にして、炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)=ソーダ灰をつくる工業的製法です。 2Na... -

硝酸の工業的製法|オストワルト法の反応式と仕組みを徹底解説
オストワルト法とは? オストワルト法とは、アンモニア(NH₃)と酸素(O₂)を出発物質として、硝酸(HNO₃)を工業的に合成する方法です。現在でも、世界中の工場で実際に利用されている代表的な窒素化合物の製法です。 硝酸は、肥料や火薬、染料、医薬品な... -

硫化鉄の化学反応式・実験方法・性質をわかりやすく解説
硫化鉄とは?|鉄と硫黄が反応 硫化鉄の化学反応式 中学校の理科では、鉄と硫黄を混ぜて加熱すると硫化鉄(FeS)ができる実験を学びます。このとき、ただ「鉄と硫黄がくっついた」わけではなく、化学反応によってまったく新しい物質ができています。 鉄(Fe... -

マグネシウムの燃焼|強い光と白い粉の正体を中学生向けに解説
マグネシウムは銀白色の金属ですが、火をつけると強い白色光を放ちながら激しく燃えます。その後に残るのは白い粉、酸化マグネシウムです。この記事では、マグネシウムの燃焼のようす、できる物質、化学反応式の覚え方のポイントを中学生向けに分かりやす... -

スチールウールの燃焼|酸化鉄ができると質量が増える!
スチールウールを火であぶると、赤く光って燃え、あとには酸化鉄が残ります。実はこのとき、鉄が酸素と結びついて質量が増えるという現象が起こっています。この記事では、スチールウールの燃焼のようすや重さが増える理由、中学生が覚えておきたいポイン...